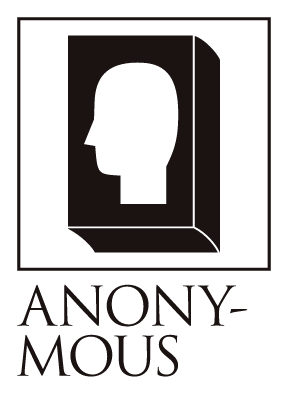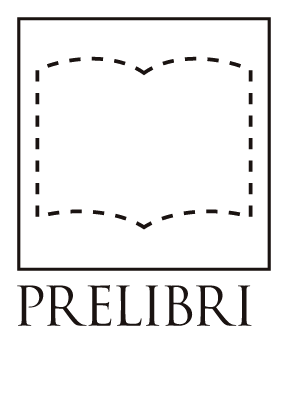Un Libro Illeggibile Bianco E Rosso / 読めない本〈白と赤〉
Bibliographic Details
- Title
- Un Libro Illeggibile Bianco E Rosso / 読めない本 白と赤
- Artist
- Bruno Munari / ブルーノ・ムナーリ
- Director
- Pieter Brattinga / ピーター・ブラッティンガ
- Publisher
- De Yong / デ・ヨング社
- Year
- 1964 (Planned in 1953)
- Size
- h260 × w260 × d5mm / cover unfolded h780 × w780 × d0.5mm
- Pages
- 36 pages
- Language
- Cover: Dutch, French, English, Japanese etc Eight languages
- Binding
- Saddle stitching with staples / 中綴じホチキス留め
- Edition
- Limited edition of 2000 copies / 限定2000部
- Condition
- Fine
オブジェとしての本を探求した
ブルーノ・ムナーリの
初代「読めない本」。
本書は、オランダの印刷会社De Yong(デ・ヨング)が1953年から1971年まで定期刊行していた「Quadrat Prints」というシリーズ刊行物の中の、ブルーノ・ムナーリが手がけた一冊。もともと、De Jong の高い技術を関係者に知ってもらう目的で企画されたPR的な役割を担っていた出版物で、De Jong 創業者の息子だったデザイナーの Pieter Brattinga(ピーター・ブラッティンガ)が同時代のクリエイターたちに制作を依頼して次々に本ができあがった。内容については、あまり口を出さなかったようで、とにかく判型が25センチの正方形になることだけが約束事だった。ムナーリの他にも、スイス人のアーティスト Dieter Roth(ディーター・ロス)や、オランダ人の写真家 Ed van der Elsken(エド・ファン・デル・エルスケン)など多士済々の顔ぶれ。
この企画は、ムナーリにとっても「読めない本」シリーズの記念すべき出版第一号となった。1940年代の終わり頃、イタリアの具体芸術運動(Movimento Arte Concreta)を牽引していたムナーリは、出版物そのものの機能と造形を「発明しなおす」野心に充ち溢れていた。その勢いで、1950年にはミラノのサルト書店ギャラリーで「読めない本」と名付けられた一連のプロトタイプを展示し、まだ1冊だけの手作り作品として「読めない本」を発表していたのだった。それを知ってたかどうかは分からないが、ブラッティンガの声がけによって、工業製品としてある程度の部数で出版することが実現したのが本書『読めない本 白と赤』である。
この本は、表紙から出版社名や著者名が消え、本文には読むべきテキストも図版もない。売り物を前提にしていないとはいえ、書物をつくるときの「お約束」をことごとく省いて、白と赤の2つの色からなる紙の造形がページを連ねていく。それに本文用紙はテキストやイラストや写真を印刷するためのもので、その紙自体がなにかを「伝える」ということはない、という常識さえもひっくり返してみせた。タイトルにある「読めない」は、文字がないことを指しているだけではなく、どのようにこの本を体験するか、読者(読者と言うべきかもわからない)の想像的な関わり方すら「読めない」ことを暗示しているように思える。
かくして、出版の歴史に燦然とかがやくオブジェとしての本が誕生した。当然、出版界の枠を超えてかなり話題になった。ムナーリもこのスタイルを気に入ったようで、その後数十年にわたって、色やサイズの異なるさまざまな「読めない本」を生み出している。文字情報にたよらないコミュニケーションを発明することは、ムナーリの本望なのだ。ちなみに、日本でいち早くムナーリに注目したのは瀧口修造で、1958年にはムナーリに会うためにイタリアを訪ねている。その滝口が序文を書くと言って、関係各所を首肯させて、1965年には伊勢丹6階の催事場で日本初となるムナーリの個展が開催された。個展に合わせて『読めない本 白と黒』も限定出版されている。滝口を通してムナーリと親交を深めた武満徹は、このムナーリの挑戦におおいに刺激を受けて、60年代後半には〈ムナーリ・バイ・ムナーリ〉という打楽器音楽を作曲する。そのときの楽譜は、五線譜の代わりに図形を用いた「図形楽譜(図形譜)」で、まだ30代の若い杉浦康平にデザインさせたものだった。
そんな『読めない本 白と赤』をデザイナーの服部一成さんが大事そうに持っていた。包んでいる紙のパッケージが、また素晴らしい。糊もホチキスも針も糸も使わない正方形の大きな紙。それを風呂敷のようにして本を包み込んでいる。そんなところも、日本文化に造詣が深く、とくに「折り紙」が好きだったブルーノ・ムナーリらしい。
text by 櫛田 理