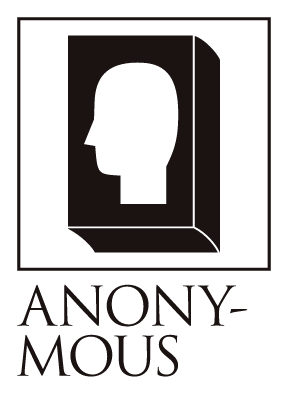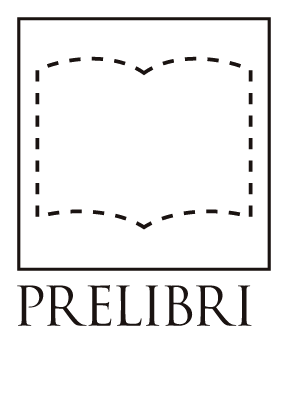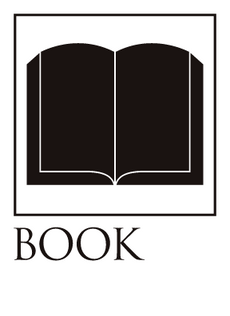主婦の友/昭和三十六年九月号
Bibliographic Details
- Title
- Shufu no Tomo, September Issue / 主婦の友 九月号
- Editor
- Sakae Morimoto / 森本 栄
- Images
- Cover Painting : Takehiko Miyanaga / 表紙絵:宮永岳彦
- Publisher
- Shufu no Tomo Publishing sha / 主婦の友社
- Year
- 1961
- Size
- h257 × w182mm
- Weight
- 540g
- Pages
- 366 pages
- Language
- Japanese / 日本語
- Binding
- Softbank / ソフトカバー
- Condition
- good
雑誌、広告、マットレス。
昭和を生き抜いた
主婦たちの夢。
雑誌という体裁の中で、いかに読者の注意を引くか編集部は工夫を凝らしたのであろう。P30とP31の間に挟み込まれた三井物産のマットレス広告は、天地が本体より短くなっている。その天地の長さの違い故、小口側にすこし飛び出した縦長の福耳が現れてしまった。タテ組で添えられたコピーは「デラックスな夢をおくる......」。最近ではデラックスよりも「高級」や「上質」などの言葉の方がウケが良さそうだが、ときは昭和三十六年である、当時はさぞ「デラックス」の言葉が輝いていたことだろう。今となっては、物珍しさから福耳の方に目が奪われてしまう。
デジタル化が進み、めっきり紙の雑誌が減ってしまったものの、今も昔も雑誌の醍醐味はそのカオスにある。本誌の「娯楽」コーナーの目次に並ぶ面子は、いまとなってはまさにデラックスだ。名前だけで失礼するが、永六輔、谷川俊太郎、手塚治虫、やなせたかし......当時はみなせっせと数え切れない小さな仕事を糧にしていたのである。
さて、総刊年に発行された本書では、「新婚の家具と室内デザイン特集」として、新婚8組の部屋やベッドやタンス、テーブルなどの新婚家具を紹介している。当時の女性たちはきっと憧れの眼差しで誌面の隅々まで目を凝らして読んだのだろう。60年以上が経った現在では、恐らく女性誌で新婚特集は組めない。この半世紀で女性の生き方や価値観が多様化し、「家庭」や「主婦」というテーマが大多数の共感を呼べなくなったことは明らかである。本を手にすると、その本がつくられた時代の暮らしの様子や社会の風潮が浮き彫りになる。こうして本が物として残り、時代を巡ることで当時の空気を伺えるのは、紙媒体ならではの魅力と言えそうだ。
«目次»
特集 新婚の家具と室内デザイン
特集 ふとんと綿
「夜と昼と」に描かれた二つの愛情
「主婦の書いた実話」入選作 がむしゃら人生
この人たちを忘れない 癩院に生きる人々
特集 小・中学生の補習教育をどうするか
特集 家庭で楽しむ抹茶入門
特集 美しくなる食事
特集 夢をかなえる利殖法
長編小説 夜と昼と
長編小説 お市御寮人
長編小説 氷の燈火
長編小説 しろばんば
-
雑誌「主婦の友」
昭和36年(1917)に創刊された日本の女性向け総合雑誌だった。主婦に役立つ情報を中心に、長編小説を複数収録するなど女性の教養も取り入れ、時代を超えて多くの女性に愛された。戦時中は苦しい庶民の生活に役立つ情報を提供すると同時に、悩み相談や読者が生活の知恵を共有する特集ページも設け、読者同士をつなぐ場も提供した。1943年には需要が増えて発行部数が約164万部に達したことも。戦後の高度経済成長期には、家庭電化製品の普及や新しいライフスタイルの特集を通じて、時代の変化に対応した情報を発信。1964年には「結婚したら主婦の友」をキャッチフレーズに掲げ、若い新婚世代から支持を得ることに成功。当時、結婚して家庭に入り、茶の間で「主婦の友」を読むことは、多くの女性にとって憧れのライフスタイルであった。しかし、女性誌の競争激化や女性の社会進出、インターネット情報の普及など、時代の変化に伴い紙媒体の需要が減少し、2008年に惜しまれながら定期刊行が終了した。
-
出版社「主婦の友社」
出版社経営者であり編集者でもあった石川武美(1887-1961)が1916年に創業した東京家政研究会を前身とする出版社。創業翌年の1917年には女性誌「主婦之友」を創刊(1954年に「主婦の友」に改題)。生活全般に役立つ情報を提供する雑誌として人気を得て、1973年には「園芸ガイド」、1988年には若い女性向けファッション誌「Ray」を創刊するなど、時代に合わせた雑誌を次々と手掛けている。現在に至るまで主婦の友社は出版社として、実用書や専門書の分野で発展を続けている。特に育児書や料理本、美容健康本など、日々の暮らしに役立つ書籍を数多く刊行し、創業以来、日本の家庭生活や女性のライフスタイルを支える存在として大きな影響を与え続け、伝統を受け継ぎながら新たな挑戦を続けている。