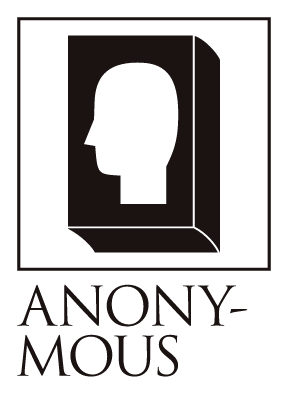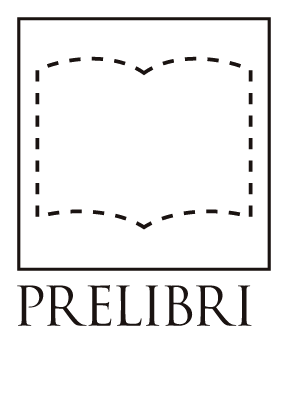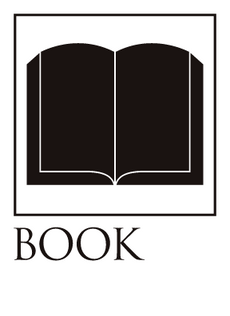日本の笛 / 北原白秋
Bibliographic Details
- Title
- Nihon no fue: Revised Edition / 日本の笛 [改訂]
- Author
- Hakushu Kitahara / 北原白秋
- Designer
- Koshiro Onchi / 装幀:恩地孝四郎
- Publisher
- ARS / アルス
- Year
- 1924
- Size
- h190 × w128mm
- Weight
- 360g
- Pages
- 474 pages
- Language
- Japanese / 日本語
- Binding
- Cloth-bound, Missing slipcase / 布上製 , 函欠
- Condition
- good(Missing slipcase / 函欠)
北原白秋の詩と
恩地孝四郎の装幀と
うつくしい福耳。
問題の乱丁は、113ページから120ページにかけて見つかった。ちょうど、白秋が八丈島や伊豆大島をうたった「椿日和」「女護(にょご)が島」「伊達のお腰」「紅い椿」のあたりに、折れた4つの折込断裁がある。100年前のものとは思えないほど、大きくてきれいな福耳である。
本の内容は、北原白秋の民謡をまとめた歌詞集になっている。「民謡は民衆の言葉を以て歌はれねばならぬ」という書き出しの「民謡私論」から本書は始まる。白秋はこの本を著した前年に「日本の童謡は日本の童謡、日本の子供は日本の子供である」という「童謡私論」を発表していて、日本の風土や幼心を忘れてしまった小学唱歌を嘆き、近代化によって狸謡が消え失せてしまうことを危惧していた。
序文を要約すると、こんなことを書いている。
馬子唄、船唄、田植え唄、盆踊り唄。たとえ、その唄をつくった人がいたとしても、その歌謡がいったん民衆の手に渡れば、たちまち民衆のものになる。郷土的なものになる。そこには、高貴な詩人の言葉なんてものはいらない。それを低俗というなら、それでよろしい。わたしのことを大俗詩人と呼びたいなら、甘んじて受け入れよう。馬子には馬子の、漁師には漁師の言葉があって、その言葉でうたうから、からだの内から燃え上がるのだ。民謡は精神の叫びなんだ。そんなことも分からない形式ばかりの詩人が増えてしまった。本当に困ったものだ。だいたいこのような調子で、白秋の声が聞こえてくるような独白がつづく。蛇足だが、白秋の4歳年下にあたる柳宗悦が「民藝」を構想し「日本民藝美術館設立趣意書」を起草したのは1926年のこと。ちょうど1920年代の半ばに、2人の眼差しが「民衆のなかの芸術」にそそがれていたことになる。
たとえば、こんな白秋の民謡が収録されている。
遠い岬
1
遠い岬に
燈(ひ)のつくころは、
なぜか眼先が、
ちらちらと。
2
そこの岬か、
幾浜先か、
とても、ちらちら、
宵燈(よひあかり)。
3
遠い岬に
燈(ひ)のつくころか、
濱にちりちり、
宵花火(よひはなび)。
先の序文のなかに、白秋自身の体験談も書かれている。すこし長いが引用したい。
私がかつて葛飾のある寒村にいた時、毎夜のように庭の木戸から這入って来る頬冠りの若い衆たちがいた。そして「唄はできているかい」である。彼等は歌謡に飢えていたのである。で、私は「できているよ」と言って、一つ二つ書いてやる。それは喜んですぐに歌いながら出ていく。そして月の夜、蛍の飛ぶ星の夜など、向こうの川べりや田園道を勝手に彼等の歌い慣れた追分や盆踊唄や都々逸などの調子に移しては流して歩くのだった。その時、私の小唄そのものはすでに彼等自身のものとなりきっていた。畢竟するに、私は彼等の歌おうとして歌えなかったものを、彼等の希望通りに歌ってやったので、それで彼等は愉悦しきったのである。民謡詩人の必要はここで生じる。
本書は、北原白秋が津々浦々のことばでうたった日本の歌が収録されている。装幀は、初版では白秋自身が仕上げたが、「訂改版」では恩地孝四郎に下駄をあずけた。恩地は、黄色のクロスで包んだ表紙には朱い箔で植物文様をあしらい、各章扉には小口木版絵を飾った。文字組みも、恩地孝四郎らしい。サイズも、袖珍本として持ち運べるサイズになっている。
ところで、版元のアルス社は、北原白秋の弟の鉄雄がおこした出版社。この「日本の笛〈改訂版〉」を刊行した2年後には、白秋と恩地孝四郎のタッグで全76巻におよぶ「日本児童文庫」刊行がはじまる。挿絵は、武井武雄、竹久夢二、初山磁、岡本帰一。編著のチームには、北原白秋と並んで、小川未明、坪内逍遙、鈴木三重吉、島崎藤村が名を連ねた。ふたたび組んだ、恩地孝四郎による装丁がとにかく出色である。
日本の笛 目次:
民謡私論
岬の夕焼
鳥の燈明
朝立つ虹
パパヤの花
椰子の日永
別れ霜
草木瓜
朱欒の港
紫まつげ
桑の葉
北原白秋(1885年 - 1942年)
福岡県柳川市に生まれた日本の詩人、歌人、作詞家で、20世紀の日本文学を代表する人物。柳川藩御用達の海産物問屋を営む旧家に生まれ、1904年には早稲田大学に入学。学業の傍ら詩作に励み、1909年に処女詩集『邪宗門』を発表。続いて1911年に詩集『思ひ出』を発表し、名実ともに詩壇の第一人者としての地位を確立。その後も、「東京景物詩」や「桐の花」などの詩集を発表し、詩と歌の分野で広く活躍。童謡集『とんぼの眼玉』や『赤い鳥』をはじめとする多くの作品を世に送り出し、特に「雨ふり」「待ちぼうけ」「からたちの花」などは、今なお多くの人々に親しまれ、語り継がれる名作となっている。
恩地孝四郎(1891年-1955年)
日本の抽象表現の先駆者であり、木版画の近代化に貢献したアーティスト。詩、版画、油彩、水彩、写真、装幀など多岐にわたる分野で活動し、特に装幀家として高く評価された。18歳で竹久夢二に影響を受け、1914年に田中恭吉、藤森静雄とともに詩と版画の同人誌『月映』を創刊。日本創作版画協会の会員として精力的に活動し、後進の指導にも力を入れた。戦後は抽象美術に専念し、作品の多くが海外に渡り評価を受ける。また、萩原朔太郎や室生犀星の詩集など、多くの書籍の装幀を手掛け、「本は文明の旗だ、その旗は当然美しくあらねばならない。美しくない旗は、旗の効用を無意味若しくは薄弱にする。美しくない本は、その効用を減殺される。即ち本である以上美しくなければ意味がない。」と語り、美しい本作りに情熱を注いだ。