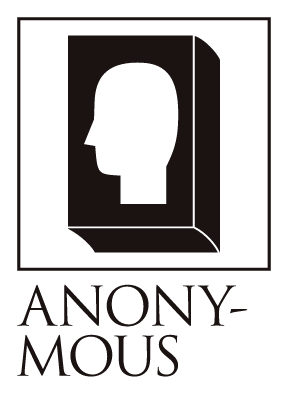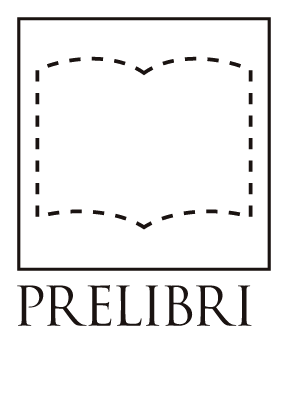Bleiben / 留まる|ヴェロニカ・シェパス
Bibliographic Details
- Title
- Bleiben / 留まる
- Author
- Durs Grünbein / ドゥルス・グリューンバイン
- Artist
- Veronika Schäpers / ヴェロニカ・シェパス
- Translator
- Yuji Nawata/ 縄田雄二
- Images
- Andreas Seibert / アンドレアス・ザイベルト
- Year
- 2018
- Size
- 680 x 520 mm
- Pages
- 1 sheet
- Language
- Japanese, German / 日本語 、ドイツ語
- Printing
- ハンブルクの版画工房ラース・ダームスによって刷られた5点のヘリオグラヴュール。奥付と注記:雁皮紙に活版印刷。Five photogravures printed by Lars Dahms in Hamburg on 70-year-old Japanese ganpi paper. Colophon and remarks: Letterpress print on ganpi paper.
- Materials
- 70年前の日本産雁皮紙に、ハンブルクの版画工房ラース・ダームスによって刷られた5点のヘリオグラヴュール。奥付と注記:雁皮紙に活版印刷。デュッセルドルフのメルゲマイヤー製本工房による、首(くび)付き・銀のタイトル箔押し入りの箱。ドイツ語原文と日本語訳の初版刊行。Letterpress print on ganpi paper. Translated into Japanese by Yuji Nawata. 3 photographs taken in Rikuzentakata and Otsuchi by Andreas Seibert. Ulrich Hennig, Director of the German X-ray Museum in Remscheid, took the x-ray images. Five photogravures printed by Lars Dahms in Hamburg on 70-year-old Japanese ganpi paper. Colophon and remarks: Letterpress print on ganpi paper. Case with embossed title by Bookbindery Mergemeier in Düsseldorf. First edition of the German text and its Japanese translation. ––– 1 sheet, about 68 x 52 cm. Edition of 28 copies using Arabic numerals and 5 copies using Roman numerals –– Tokyo, 2011
- Edition
- アラビア数字28部、ローマ数字5部 / Edition of 28 copies using Arabic numerals and 5 copies using Roman numerals
- Condition
- New
あの日は
一冊の本に留まりつづける
問題の本質と共に
東日本大震災のボランティア活動を機に制作を開始したアーティストの瀬尾夏美は、震災を題材とした著書『二重のまち/交代地のうた』を刊行した理由について「誰かが忘れずに、覚えていてくれるように。そして同時に、誰もが忘れてもいいように」と書いている。また、ヴェロニカとは異なるタイプの(正反対とまでは言わないまでも)ブックメーカー、イルマ・ボーム(Irma Boom)は小さな赤い著書の中で、「本は未来のために作られる。情報が変わることなく、凍結されていることが、過去と未来をともに理解する鍵になる」と語っている。
ヴェロニカは、この本の中に自らが経験した「3.11」を凍結し、綴じ込めた。カチッとした黒く四角い化粧箱は、タイムカプセルさながらに寡黙にあの日を封じ込めている。私たちが不在となる未来で、あの日についての理解を助けるために。
あの日、ヴェロニカは東京にいた。日本に暮らしていたのだ。さまざまな方面から噴出するありとあらゆる情報に押し潰されそうになりながら、人として、母として、ブックメーカーとして、この震災と人災の本質をどのように見定めるのか、ヴェロニカは考え続けた。放射能への恐れと余震の続発から、震災発生のわずか2日後、家族とともに福岡へ避難した。そこから香港とドレスデンを経由してデュッセルドルフへ移動し、5週間滞在したのち東京に戻っている。このドイツ滞在中、短期間であったにも関わらず、使命感に駆られた彼女はこの本のためにX線を使ったプロジェクトに着手していた。
X線を使うことを思いついたきっかけは、放射能の「不可視性」だった。影響があらわれるのは何年、あるいは何十年も後になるかもしれない。その見えないエネルギーこそが、ドイツに一時帰国していたヴェロニカが考えつづけた問題だった。二人の幼い子どもを連れていつ東京に戻るのか...。「見えないもの」を可視化するために、彼女はX線を使うことを思いつき、読み手には「見えない」工程を本に加えることにした。
X線で撮影されたのは一片の詩だった。ドイツの詩人で随筆家のドゥルス・グリューンバイン(Durs Grünbein)が、この本のために書き下ろしたもので、ドイツ語とあわせて縄田雄二による日本語訳が併記されている。
留まる ードゥルス・グリューンバイン(縄田雄二訳)
福島の翁と嫗。
レポーターに慇懃に説いて曰く、
ふるさとを去りはせぬ、
何者もわれらを連れ去れぬ、と。
磨きたてた木の床に膝をつきつつ笑む。
年金暮らしのともしらが。
太平洋岸のフィレモンとバウチス。
大波が港を呑んだ。
いまや誰にも見えぬ影が忍び寄る。
二人には分かっている。過去はもはや無いと。
有るのは末来と笑みだけと。持ちこたえるのだ、
酒が蔵にある限りは。
ヴェロニカが、詩のX線写真に寄り添うようにレイアウトしたのは、スイス人写真家アンドレアス・ザイベルト/Andreas Seibert が、震災直後に撮影した陸前高田と大槌だ。津波によって壊滅した陸前高田を歩きながら、遺物を探す女性や、倒壊した家屋に残されたままのアルバムを写した。これらの写真は、ハンブルクの版画工房を訪ねて古典的な銅版画技法で墨一色に刷られ、記録という機能を超えて抽象芸術の域に達している。
本の佇まいは、四角い。曲線のたおやかさを本のかたちとしてあらわすことを得意とするヴェロニカにしては、その直線の連続にどこか頑なな印象も受ける。箱を開けると、漆黒の紙に挟まれた大きさの異なる雁皮紙があらわれる。畳まれた雁皮紙をひろげると、銅版で刷られた写真やテキストとはべつに、無造作に手書きされた数字や名前がところどころに見える。この雁皮紙は、70〜80年ほど前に産地で手漉き和紙を包むために使われていた和紙で、包まれた和紙の数量や和紙職人の名前などが手書きされたままの状態で残されていた。粗末に扱われていたために赤茶けた色や、経年変化によるヨレやシワが、より一層あの日の大地のズレを思い起こさせる。「今日、その問題の本質は自分ごととして捉えられているのか」とでもいうように、封じ込められた時間の波が押し寄せてくる。
YOKOTA TOKYOの横田茂さんは、過去にわたしたちのインタビューにこう話してくれた。「本質的なことを考える人間が減っていると感じています。いまこの時代にコミットしているということ、社会的なメッセージ、そこに生きる人間にしかできない仕事をするべきなんです」と。さらに続けて「”いま、あなたは何を問題にしているのか?”という、頭で思考するのではなくて、この時代の空気を吸って、日本の地べたを這って、社会に対するメッセージを発している作家がどれくらいいますか?」と、こちらをじっと見つめて問い返した。
ヴェロニカは日本人ではない。けれども、あの日を体験したアーティストの一人として、その本質を考えることを諦めていない。この時代の空気を吸って地べたに這って、社会に対するメッセージを一冊の本にして出すことを止めない。それは、彼女自身の存在の証でもあるからにほかならない。